
道徳の授業の準備が一番大変です。毎回プリントや板書などを考えておかねばならず、大変負担になっています。

そうですね。道徳の授業は、気合いをいれて準備しないと、うわべだけの授業になってしまいますからね。少しコツがあるのでそれをつかめば、楽になりますよ。解説します。
毎回道徳のプリントを作るのは大変ではないでしょうか。
少なくとも、私はそのように感じていた時期がありました。「道徳が無かったらもう少し、授業の負担も少ないのに・・・。」なんて思ってしまったものです。
しかし、道徳の学習に全力で取り組めば子供たちも変わっていきますし、私たちもやりがいが出てきます。
今回は、そんな大切な道徳の学習の準備が少しでも楽になれるように、道徳の万能プリント、万能ノートを紹介します。
「道徳の時間」「道徳科」万能プリント・万能ノート
万能プリント
紹介する万能プリントが下のものです。
 Loading…
Loading…
使い方は簡単です。
めあてを書き、1の項目には、教材の価値に関するものを。
2には、自身の考えを書くようにしています。
そして、最後に自身のことを振り返って、自分にも同じ価値があるかどうか、また、これからどうしていきたいかを書かせます。
使い方は自由。大事なのは処理の効率。
万能の形式の理由
なぜ、この形式が良いのでしょうか。
この形式は、主に、「めあて」→「補助発問」→「主要発問」→「価値の自覚化」が図れるようにしています。
道徳の学習は、大まかにこの流れをはみ出すことは無いので、この形式が成り立ちます。
実践例
例を挙げます。対象は6年生3月。「めあて」は割愛します。
次の2つの詩の内、みなさんは、どちらの考え方が自分に合っていると思いますか。
A
ぐちをこぼしたっていいがな
弱音を吐いたっていいがな
人間だもの
たまには涙をみせたっていいがな
生きているんだもの
B
長い人生にはなあ
どんなに避けようとしても
どうしても通らなければならぬ道というものがあるんだな
そんなときはその道をだまって歩くことだな
愚痴や弱音は吐かないでな
黙って歩くんだよ
ただ黙って
涙なんか見せちゃダメだぜ
そしてなあ その時なんだよ
にんげんとしての
いのちの根がふかくなるのは
Aの考え方、または、Bの考え方どちらが自分に合っているかを選び、理由を「1」に書きます。
この時点で、子供たちは、「A」もしくは、「B」の立場をはっきりさせ、学習内容に入るでしょう。
そして、Aを多くの子が選び、Bも何人かが選び、どちらが正しいかを話し始めるでしょう。
学習ノートの「1」の欄は、その理由でいっぱいになっていることでしょう。
「1」に書かれていたのは、2つの違い。
でも、実はAもBも、同じ作者である相田みつをさんが書かれたものです。
同じ人なのに、弱音を吐く吐かないと、言っていることが違うのは、おかしいですよね。
ですから、どちらが正しいというものではないということを認識させます。
言っていることはちがっても、同じ人が言っていることですから、伝えたいことは同じはずです。
そこで、今度は、2つの詩に共通して作者が伝えたいことを「2」に書かせます。
すると、人生いろいろあっても、愚痴を吐いたり、力強く踏ん張って突き進むことが大切ということが結論として出てきます。
子供たちの人生の中にも、同じように困難だと思ったことを愚痴を言いながら乗り越えたり、強く突き進んだ経験があると思います。
それを最後の欄に書かせてください。
班でそれらを出し合って、お互いを励まし合って終わりです。
必ず教師が、コメントを書いて返却してください。
「道徳の時間」万能ノート
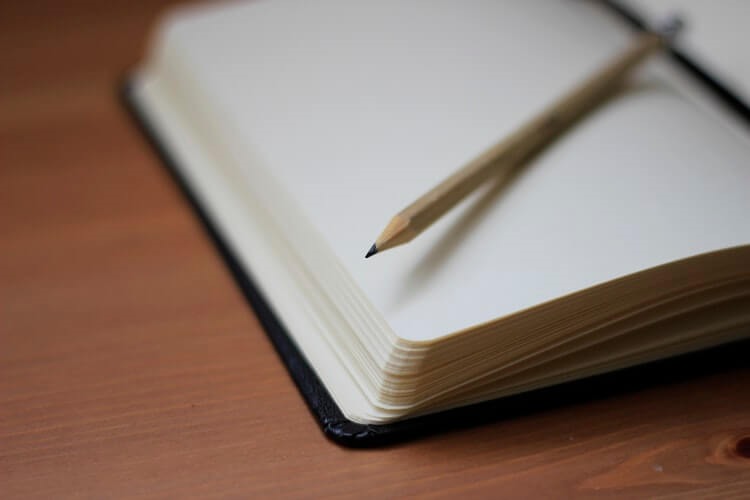
また、そのプリントすら作るのが面倒なときは、ノートに同じ形式で書かせてみるのはどうでしょうか。
これは、ノートであればなんでもよいのですが、ある程度プリントで慣らしたら、ノートに書かせていきましょう。プリントを印刷する手間が省けるからです。
また、プリントではせっかくたくさんいいことを書いて、先生も良いコメントを書いてもぐしゃぐしゃになって捨てられます。
きれいにプリントをとっておける子はいいのですが、そんな子は道徳的な価値観も高いのです。
ぐしゃぐしゃにしてしまう子ほど、道徳的価値を何度も片付ける必要があります。毎回集めて無くさないようにさせましょう
ただ、ノートなら捨てられる可能性は少なくなります。また、教師の褒め言葉が繰り返され、反復効果も期待できます。
まとめ
今回は、道徳の万能プリント・ノートでした。
コツを掴めば、道徳の流れは、教師の中にも、子供たちの中にも定着して学びやすくなります。
欲張らず、全体の仕事量を考えて使用してくださいね。それでは。

