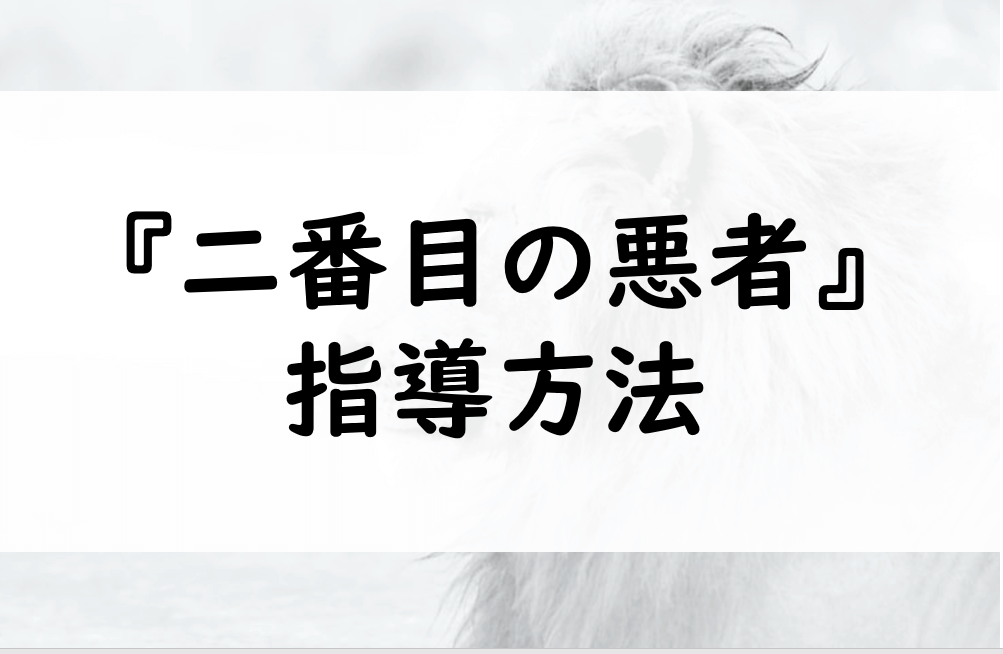うちのクラスで友達に対するいやなうわさをながすことが流行っています。なにか良い教材はありませんか。

高学年になるにつれて、そのようなうわさ話が好きな人がたくさん出てきますからね。「2番目の悪者」という絵本はどうでしょうか。

どのようなお話ですか。

簡単に言うと悪いうわさによって、国が滅びた話です。解説しますね。
今回は、『2番目の悪者』(林木林作)を使った学習について記事を書きました。
うわさがでたときの自分の身の振り舞い方としてどうあれば良いかを考えることができます。
いろいろな情報が飛び交う今の時代にぴったりな教材ですね。
どのような教材利用をするか

うわさを確かめずにすることの愚かさを学ばせる道徳・人権学習として扱うことができます。
・小学校低学年用で読み聞かせ。
・小学校高学年で道徳・人権学習。
・全校集会で読み聞かせ。
というような教材活用方法が考えられます。
少し、物語の終わりの方の情報が多いので、読み終わったあとに、整理をしてあげると良いですね。
絵本の内容

あらすじをみていきましょう。
次の王様になりたい金色のライオン。
一方、銀色のライオンは良い人で王様に適任だと評判だった。
銀色のライオンの評判を落とすため、金色のライオンは悪い噂を流す。
王国の動物達は、その噂をほとんどの人が確かめもせずに信じ、金色のライオンが次の王様に就いた。
しかし、金色のライオンの自分勝手な政治のため、国は滅びてしまった…。
『2番目の悪者』の登場人物は、シンプルで、「金色のライオン」、「銀色のライオン」とその他の周りの動物です。
子ども達には、周りの動物の気持ちになってもらうとよいですね。
国が崩壊した後の動物たちの言葉
「もし、銀のライオンが王様だったら、こんなことにならなかったのに」
「そうさ、彼こそがふさわしかったのに」
「僕はただ、銀のライオンに気をつけてって聞いたから、仲間に教えただけだよ」
「私だって、なんとなく心配だったから、家族に知らせただけだわ」
「おいらだってちょっときになって、メールを転送しただけさ」
金色のライオンの他には、悪意のあるものなど誰一人としていなかった。
これらが金色のライオンによって国が滅ぼされた後の言葉です。
どの人も関係ない口調で責任を逃れようとしています。
しかし、野ネズミは、次のような言葉を言います。
野ネズミ
「僕は聞いた話を、友達に教えてあげただけなんだよな。でも、自分の目で何か一つでもたしかめたっけ・・・・・・?」
野ネズミも、ただ伝えただけと言います。
しかし、自分の目で何かを一つでも確認したかという疑問にも気づいています。
知らず知らずのうちに、やっていたことが、悪い結果をもたらしたということに気づかせたいです。

Twitterのリツイート機能などで何も考えずに多くのことを拡散できる時代ですからね。身の振る舞い方を考えさせられる時間になると考えられます。
銀色のライオンは一番良い?

子ども達に、尋ねたいのは、銀色のライオンは一番良い人なのかということです。
人権学習をしっかりしている子は、これをNOと言うでしょう。
しかし、学んできていない子は、金色のライオンと比べて、銀色のライオンは一番良いと結論を出します。
銀色のライオンの行動を整理すると、
・周囲の動物に対して優しかった。評判があった。
・金色のライオンに、噂を立てられた。
・ただ苦笑いをし、誤解が解けるのを待った。
優しく評判があったのは良いことでしょう。しかし、噂を立てられたときに、何もしなかったのでは、自分の人権は守れません。
・間違っていることは、「間違っている。」
・していないことは、「していない。」
様々な情報が飛び交う中で、正しい情報と誤った情報が行きかう世の中です。誤解が解けるまで待つのではなく、正しい情報を発信していくのも自分の人権を守る手段なのではないでしょうか。
指導方法 (高学年編)
うわさをしたことを簡単に振り返る(アンケートで)
・「○○さんって▽▽だよね。」とうわさをしたり聞いたことがありますか。
・「○○さんって▽▽らしいよ。」とうわさをしたり聞いたことがありますか。
・「あなたは、本当かどうかわからない情報をだれかに伝えたことはありますか。」
ほとんどが、「あった」と応えます。
していないと答えている人は、した実感がないだけで、恐らく経験はあると考えられます。もしくは、これから必ず起こることだと考えてもらいましょう。
そして、そのうわさが出たときに大切な心に目を向けられると良いですね。
「うわさを聞いたときに大切なことを考えよう。」

めあては実態によって、変えられてください。私は、めあての時間は限りなく、ゼロに近づけたいので、短くしています。
本文を読み内容の確認
教師が、音読して読んでください。教師が音読することで教師自身も内容を改めて確認できます。
これは、教材研究の時間短縮の意味でも意味があります。
1番悪いのはだれ?1番悪くないのは?
2番目に悪い人はだれかを考え、話し合わせます。
でもその前に、1番悪いのはだれかを考えさせしょう。子ども達は、金色のライオンと即答します。
逆に一番良いのはだれかと問うと、銀色のライオンと答えます。
もしくは、勘の良い子は、銀色のライオンは一番よくないと応えるかも知れません。
2番目に悪いという対象をしぼりこむ
絵本の中では、次のようなセリフが出てきます。
- 「あの街外れに住む優しい銀のライオンが、仲間をなぐって食べ物をうばったって聞いたけど、そんなことあるわけないよね」(ねずみ)
- 「銀のライオンが実は乱暴だって話も出ているの?」(うさぎ)
- 「なんでも、投げ飛ばされた相手がけがして入院したとかしないとか……」(ねこ)
- 「救急車が止まっていたよ。もしかすると、あれがそうだったのかなあ」(きつね)
- 「ねえねえ、聞いた?昨日は、あの暴れ者のトラとなぐり合っていたらしいわよ」(ラッコ?)
- 「うそでしょ?」(鳥)
- 「しかもいきなりとびかかっていったみたい」(ラッコ)
- 「え、ほんと!?」(鳥)
- 「僕も銀のライオンがトラに襲いかかるのを見たって聞いたよ」(犬)
- 「私も友達から聞いたわ。はでにもみ合っていたって」(ラッコ)
- 「君も聞いたのかい、そのこと」(犬)
- 「まさかって思っていたけどさ、乱暴者だっていうのは、ひょっとすると本当かもしれないね」(ねずみ)
- 「たしかにね、みんなそう言っているし……、火のないところに煙は立たないっていうからね」(うさぎ)
- 「近寄らないほうがいいかも」(ねこ)
- 「関わらない方がよさそうだ」(きつね)
- 「シカくん、銀のライオンには気を付けてくださいね。」
- というメールをリスクくんに送り瞬く間に広がった。(シカ)
- 「銀のライオンは、それはそれは親切でりっぱな方です。台風でこわえた私の家を泥まみれになって治してくれたんです。」(ふくろう)
- 「ヒナだった僕が巣から落っこちたときだって、汗びっしょりになって巣に戻してくれたんだ。悪い評判なんて何かの間違いさ。」
これらの人物を、図や言葉で整理してあげると良いですかね。
自分の考えをもち、図に書き込む
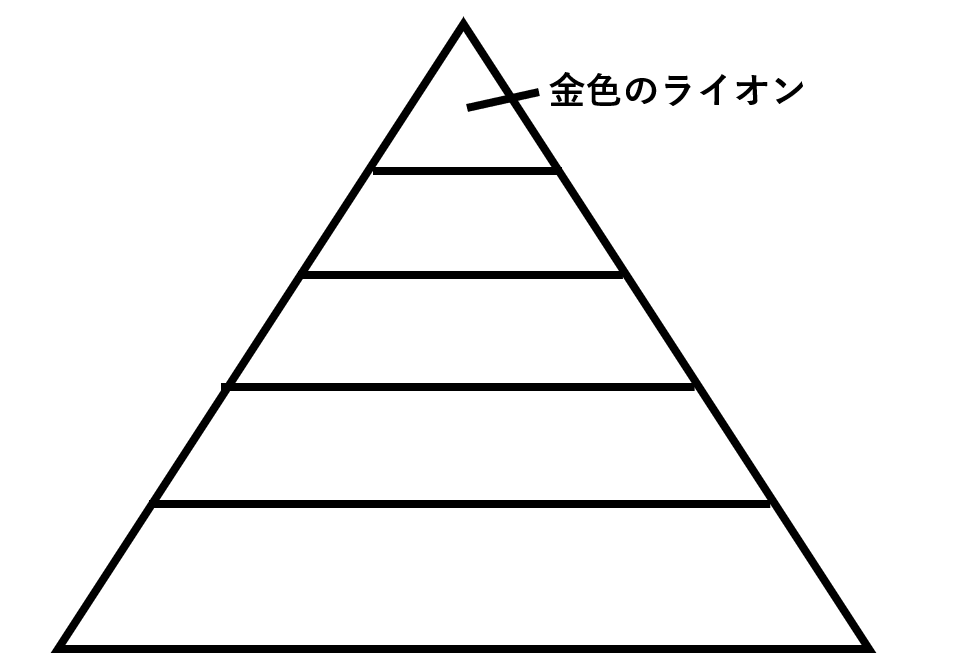
金色のライオンが1番悪いとわかっているので、悪い順に書き込ませます。そうしたら、2番目に悪いのはだれなのかを、考えさせることができます。

みんな同じように悪いんじゃないかな
という子が出てくると思いますが、「あえて2番目をつけるならだれ?」と聞いてみると良いでしょう。
まずは自分の考えを図で表せて、交流させましょう。名前が移動できるようにカードを用意してあげておくとより良いです。
グループごとで話し合わせ、結果を発表させる
グループごとで話合わせて、発表させます。発表するという目的意識をもっておくと、必然的に話し合うでしょう。その意見の交流をしながら、どの行動も愚かな行動だと気づくことができます。
また、その際に、この結論はまとめず、オープンエンドで終わると良いと思われます。
「いっぱい話しましたが、結論はありません。お家の方に聞いて、自分の意見を伝えてみましょう。」
といって、振り返りに入ると良いかと思われます。
無理に、誰が2番目と決めてしまうと、本人たちの思考の流れを止めてしまいます。この学習で大切なのは、うわさがあったときに自分の身の振る舞い方を考えさせることです。
自分をふりかえる
話あっていく中で、自分がありたくない姿が出てくるでしょう。その思いやこれまでの自身の姿をまとめられる良いですね。
うわさを確かめずに人に伝えることは、いけないことだとわかった。今まで、家族や友達から聞いたことは全て確認せず友達や家族に話していたので、しっかり確かめてから話したいと思いました。
実践ロールプレイをする
実際に、子どもにだれかが噂話をしてきたという設定で、自分考えた行動を実践する。
学習時間が余ったら、実践ロールプレイをしましょう。思って考えるだけでは、実際に行動に子ども達は移せません。
なので、実際に同じようなシチュエーションを設けて、やってみると記憶に残りやすいです。全員に問いかける形で、全員に反応させましょう。
「○○さんが家庭の事情で休みだね。多分、新型コロナウイルスだろうね?」
「あの人いつも暴言を言ってむかつくよね。この前本段がめちゃくちゃになっていたのも、あの人らしいよ。」
良い反応ができたら、たくさんほめてあげてくださいね。
まとめ
今回は、「二番目の悪者」で道徳・人権学習教材を考察してみました。
新型コロナウイルスなどであやふやな情報が飛び交いう情報化社会の中で、「うわさ」について考えることができる良い教材だと考えました。
みなさんも、是非活用されてください。

情報過多の時代。確かめもせず、批判やからかいをする人に一石を投じる良い教材です。悪意のある情報に踊らない、踊らせない人に育ってほしいですね。それではまた。