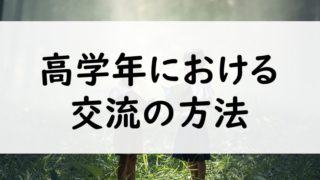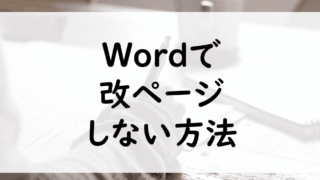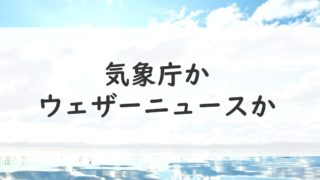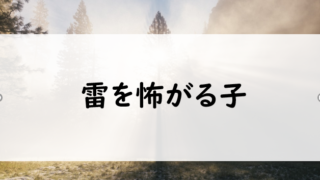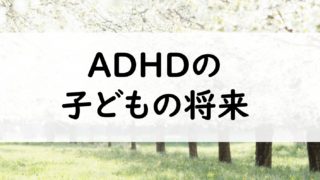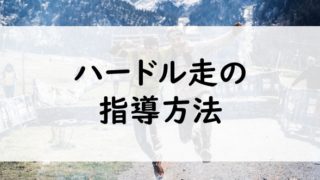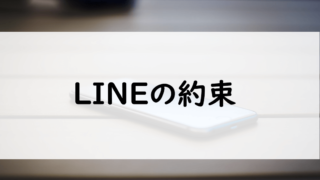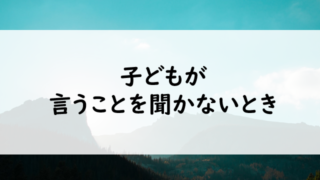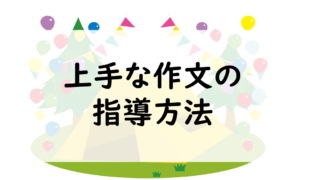初任者指導をしています。初任者の学級で授業中にものが飛ぶとか物をとるなどのいたずらが相次ぎ、いじめに相当するトラブルも出てきています。なんとか自力で解決してほしいとアドバイスを送りながら、間接的に学級経営をしています。この状況で、自力解決は可能でしょうか。

なるほどですね。自力での解決は正直申し上げて難しいというのが結論です。早急にまじめに頑張っている子どもをすぐ守る対策が必要です。解説します。

よろしくお願いします。
今回は、少し荒れている学級をみて「これはまずいな…」と思ったときにどうするかについてです。
この「学級がまずい」状況というのは、若手の先生だけでなく、中堅の先生やベテランの先生の先生でも十分起こりうることです。
子どもと教師の間で、何かしらの意思疎通がずれて、少しのずれが大きくなっていくのは、どの学級でもあり得ます。
そんな状態になっているのに、「これも経験だから」と言って、その担任の先生方を見放さないで下さいね。それでは、解説します。
「まずいな…。」の線引き
一口に「まずいな。」と言っても、様々ありますよね。でも、単純です。
「教師の言うことを聞けていない」という状態です。
「教師の言うことを聞いていない」ときがまずい状態
教師の言っていることを子どもが聞いていないような状態は、つまり、学級崩壊している状態です。
それらは、担任の自力解決は困難です。
不注意や手遊びで「聞けない」ではなく、この先生の言っていることは信用ならないという意味での「聞かない」となっています。
別の見方をすると、他の先生が入ったらクラスが落ち着くねと言われたら危険と思われて下さい。大きなトラブルが起こる予兆です。

いじめ、物かくし、暴力、うそ等保護者を絡む大きなトラブルが待っています。多くの真面目な子が傷つき、多くの子どもと保護者を不安にさせてしまいます。
それではどのような対策が有るのでしょうか。以下の例を見てみましょう。
学級を崩し、学年で包みに行く
学級を崩し、同学年で包みに行く。
担任と関係を築けない子でも学年の他の学級の先生とは築ける場合が多いです。
むしろ、同学年の先生と様々な面で比べられてしまって「まずい状態」が起こる場合があります。
崩壊している学級だけができてないと伝えるのではなく、全学級でできていないと認識させることが大切です。
その場合週に2回から3回、学年会を開き、その学級の問題として扱うのではなく、学年全体としての課題ととらえさせることが大事です。
学年のどの学級でも「聴く」ができていないと認識させるのがポイント
・「現時点で学年度してこのような課題がある。」
・「これらの問題は、みんなにとって損である。」
そのような話をすると良いです。
話すのは学年主任の先生だけでなく、全員の先生が言うと効果的です。
話さない人は、下の身分の人なんだと子ども達はとらえてしますからです。
担任の先生の授業が成り立たない場合は、担任の先生に子どもたちが教師なしで夢長いになれる図工などをしてもらいます。
他の教科を同学年の先生がするという対策がとれます。
朝の会、帰りの会なども他学級の先生が行い、関係が崩れているところを分散させる手段もあります。

担任が逃げたと思われないように、中学校になったら教科担任だからなれないといけないねなどといって、先手をうっておきましょう。
複数教師を配置・視認させる
複数教員を配置・視認させましょう。T.Tだと言って、教務主任が教室後方で作業するなどするだけでも、落ち着いて学習する子が増えます。
また、教師が教室に複数いて、休み時間や始業前、終業後もしっかり見届けることで、重大なトラブルは未然に防げます。
子どもを見るだけでなく、担任の先生の間違った行動を抑制することができます。
やはり、学級が荒れてうまくいかないときは、担任はストレスが高い状態にあります。
そこで必要以上に大声で叱責したり、大きな音を立てたりする場合があります。
それは、担任の先生にとっても、子どもたちにとっても、嫌なことです。
複数教員を配置することにより、それは防げます。
それを未然に防止するためにも、複数教員を配置することが良さそうです。
担任を交代する
担任を交代するという手もあります。しかし、これはあまりおすすめはしません。
この方法はリスクがあって、担任の先生を大きく傷つけてしまいます。また、子どもも担任の先生を一人倒したといって勢いが出てしまいます。
しかし、本人の希望のもと、本人が学校の業務を改善できるのであれば教務と担任を交代するなど、役割を交代ができるのであれば解決策の一つに成り得ます。
前任校で研究主任をしたり、国立大学の付属小学校などで成果を上げた優秀な方が転勤先の学校で荒れた学年をもたされ、合わず、教務と交代する例はよくあることです。
その方の人生を狂わせないように、大事にしていく必要があります。
そのままの担任だけではだめか
関係が築けていない時点で、早急な対応は一人では無理です。
「担任としてのプライドを傷つけてしまうのではないか。」 「本人の勉強にならないのではないか。」
という考えはわかるのですが、それではいけません。まずは子どものため、その保護者のために私たちはやれるだけのことをしなければなりません。
いつ何が起こってもおかしくない状態ですので、担任の言うことを聞けていない状態に気づいた時点で、対策を始めましょう。
配慮を要する担任の場合
「プライドが高い」「情緒的に不安定」の先生の場合は、配慮が必要です。
本人が精神的につらくなってしまいますので、そのような先生の場合は、次のようにしましょう。
・ティームティーチング指導としてT2・T3で入る。 ・気になる子対応として部分的個別指導として入る。
上手に交渉して、学級が大きく崩壊しないような入り方をしていきましょう。
まとめ
・学年で対応する ・複数教員を配置する ・担任を交代する
以上です。
もやっとしますよね。解決になってないと。でも、自力で解決させようとしたとき、ほとんどの場合失敗します。それほど、一度切れてしまった関係を修復するのはかなり難しいことです。
でも、3月の修了式までほとんどの場合担任はそのままです。
そして、次の学年の方が学級が鍛えられてなくて困ります。担任の先生も学校に来るのが億劫になります。何より真面目に頑張っている子どもたちも…。

子ども、学級は学校や地域、みんなで育てるもの。だれも苦しまないようにチームで対応していきましょう。それでは。