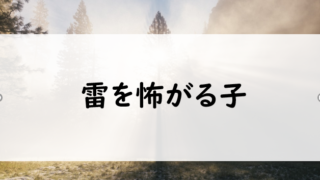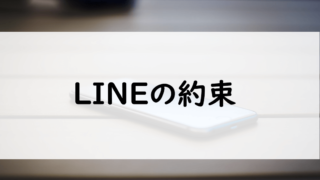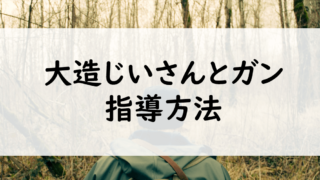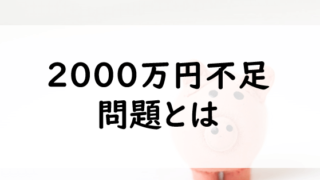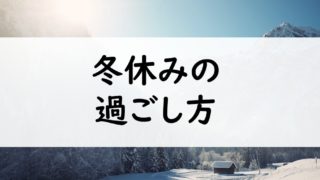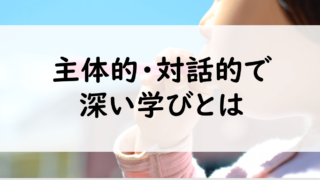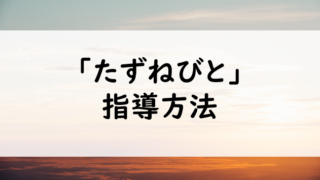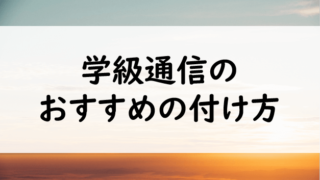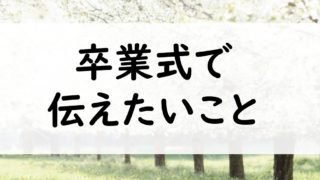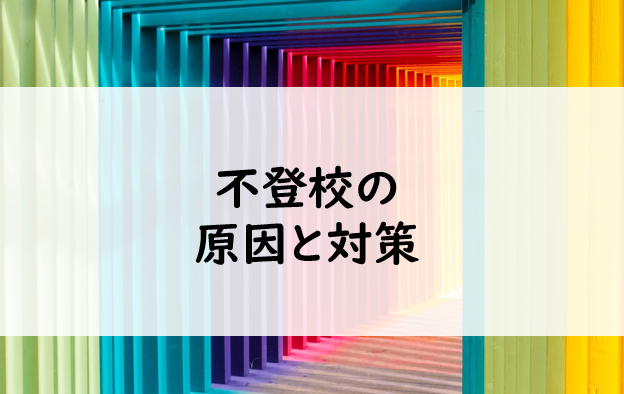こんにちは。突然ですが、うちの子どもが不登校になってしまいました。もともと神経質だったのですが、3年生ごろから言葉使いが悪くなり、学級の友達の悪口や担任の先生の不満を言うようになりました。そして、「学校を辞めた」と言って行かなくなってしまいました。

こんにちは。それは、お子様もお家の方も大変な思いをしていますね。

はい。子どもも、友達のせいや担任のせい、お母さんのせいと言っていることがころころ変わり、原因の特定ができません。そのせいで私も気持ちがめちゃくちゃになってしまっています。

すごく想像がつきます。そして、多くの親御さんも同じ思いをしていらっしゃいます。ですから、まずは肩の力を抜いて私の話を聞いてくださいね。
今日は、不登校の原因とその対策について述べていきます。
これは、社会問題になっている引きこもりにもつながることにつながるかもしれません。
この記事を読んで、短期的な解決ではなく、長期的な目線で考えていけるようにしていきたいですね。
なお、この記事は、心理的に不安的で数日休む欠席と異なる年間30日以上欠席をしている子を対象として書いています。
不登校の原因

実は,原因は無いことの方が多いです。
先に結論をかきましたが、不登校には原因というものがないことが多いです。
大人は焦って、友達関係のせいや、先生が何かしたとかあらゆる原因を模索しがちですが、不登校になる子は突発的な原因というものがないことが多いです。
先にそれを知ったうえで読み進めてください。
人間関係の原因
先生との関係
先生との相性が合わないということがあります。
これは、ほとんどの場合先生に非はないのですが、子どもがうまくいかない原因を先生ととらえ、担任の先生や担当の先生に原因があるといわれることはまれではありません。
もちろん、担任の先生とのうまが合わない場合があります。担任の先生の声が大きい。話の内容が理解ができないことなどです。担任の先生は、学級のため、その子のためを思って話をしているのですが、伝わらないことも、多いものです。

私も若いころ、友達を意味もなく殴った子を大声で指導していると、全く関係のない子が傷ついたことがありました。その感覚は、なかなか若手の先生にはわかりにくいことです。
しかし、担任の先生だけを厳しく糾弾するのだけはやめた方がよいです。担任の先生を攻めて、解決するような問題ではありません。結局、担任の先生は不登校の原因にしやすく学校も攻めやすいので、保護者の方で、事実をよく知らず一方的に学校を批判して満足される方は少なくありません。
むしろ、担任の先生は良いケースな場合が多いです。
感情的になって、学校からの連絡を拒んでいると、取り返しのつかないものになります。これからの社会復帰には担任の先生が必要不可欠なわけですから、早まった糾弾は逆に子どものためになりません。
友達関係
友達関係がうまくいっていないことから学校へ行きたくなくなるということがあります。
けんか。にらまれたことなど多岐にわたります。
うまく友人の前で笑えなかったり、うまく人間関係を築けずに、学校を休んでしまうことがあります。
また、何もないけれど友達のせいにしてしまうこともあります。
家族・家関係
家族の関係で行けなくなることがあります。
・経済的な理由
・家族の介護
・家が遠い
・親の不和
・赤ちゃんが生まれて赤ちゃんがえりをした
家族の居心地がよいので学校へ行けなくなることがなります。

経験上、家の遠い子や赤ちゃんがいる家庭、親が不和なところは不登校傾向になる子が多いです。子どもの心が不安定になるのでしょうね。しっかり、見守ってあげたいですね。
学校という空間
学校という空間そのものに抵抗をもっている場合があります。
騒音や緊張感。そういうものが繊細な子は耐えられず体の不調につながる場合があります。
幼少期、怒鳴られ続け落ち着いていたように見えても、かなりストレスで潜在的に学校=我慢、強制等不自由なイメージで縛られてしまいます。
起立性調節障害
自律神経が乱れていて朝体調が悪くなることがあります。
それは、起立性調節障害が原因かもしれません。
そのような子は、日中も顔面が蒼白で、朝腹痛や吐き気があり、昼に回復する傾向があります。
そのような子は午後から学校に来ることなど対策が必要になります。
絶対に行けないのは、勝手に怠けていると決めつけて、無理矢理つれていくことです。10歳までらはこのようなことが通用することもあるのですが、体が大きくなるにつれて反発と拒絶心が大きくなります。
完全に不登校にならないうちは、本人のペースでいかせましょう。
学習性無力感

実は、私もこれでした。原因なんてないのですが、突然全てのものごとにやる気が無くなってしまったのです。
突然原因もなくやる気が無くなってしまう状態です。真面目な子供に限って、これになります。私は、高校時代友達関係もうまくいき、成績もまあまあ。先生方からもよく扱ってもらっていました。
しかし、高校1年生の終わりに友達が学校を辞めた時、無性に、「学校なんて行く意味ないな。」と思ってしまいました。欠席がちになり、親の努力でなんとか学校前まで車で送ってもらいました。高校2年生のとき、心が整って、残り2年は休まず学校へ行き、なんとか卒業できました。
あるところで、中学生が病死し、その一番仲の良かった友達が飛び降り自殺をしました。それに似ている感じかもしれません。
こればかりは、思春期ならではのよく説明できない感情です。結局、なんであんな時期があったんだろうと今でもわかりません。あれ以来、私は学校を休んだことはありません。
HSC
最近流行ってきた言葉です。ささいなことにも敏感に感じてしまう過敏な子のことです。
音や言葉かけ、何に対しても過敏になってしまうようです。他人の些細な言動や仕草で傷ついてしまいます。
これは、以前から気になっていたのですが、生まれたときから音や大人の反応に過敏に反応する子がいます。逆に全く反応しない子もいます。その過敏に反応がある子は要注意です。
友達が大人から怒られており、全く関係絵が無くても泣いてしまいます。友達に感情移入をしすぎてしまいます。
「みんなを守りたい」「強くありたい」と心で思ってしまうばかりに自身を傷つけてしまいます。
担任や、親の力を使って自立させようとしても難しいです。あらゆることを気にしてしまうので、全てが逆効果になります。
友人らの力を使って登校させようとしてしまうと深刻なダメージを受けてしまいます。
あくまでも本人のペースで自信をつけさせる取り組みが必要です。できることだけをし、できることを増やしていく取組が必要です。本人が興味をもちそうなことを幅広くさせて、心にエネルギーがたまるのを待ちましょう。
経済的理由
近年は少なくなってきましたが、金銭的事情で行きたくないという子がいます。
これは意外と見落としがちです。以下のようなケースがあります。
・みんなと同じ絵の具を買ってもらえない。
・みんなと同じリコーダーを買えない。
・服がいやだ。
・スマホがない。
・○○というゲームがない。
意外にも子どもの中では心理的なダメージは大きいように感じます。特に高学年の女子では多い傾向にあります。

スマホは賛否両論ですね。よく家族で話し合われて契約されると良いと思います。
そもそも原因なんてない
多くの子どもの場合、これが当てはまるのではないかと思います。原因はないのだけれど、ただ学校へ行くのがきつい。原因は何もない。といったものです。
家という安心安全で自由でのびのびできるところに対して、学校というのは不便で窮屈で不自由な空間です。本能的に行こうとはだれしも思うことができません。
どんなに素敵な学校で素敵な担任の先生で素敵な友達がたくさんいたとしてもです。しかし、大人たちは、「原因は何?」と問います。子ども達は苦し紛れに応えます。正しい回答ではないのにです。そう言って面倒なその場をしのぐのです。ですから、問題を一面的に考えがちな保護者の方は味方を全て敵にしてしまう恐れがあるので危険です。
原因をつめても意味がないことが多い。

「原因はこれか!」「原因はそれか!」としていっても、堂々巡りです。聴くだけ聴いて、どうするかの軸は、専門家と話し合って決められた方が良いです。
不登校の対策
一度すべてを捨てる
一度すべてを切り離しましょう。特に以下に挙げるものです。
・学校に行かなければならない。
・勉強しないといけない。
・仕事に就かなければならない。
大人からみた素敵な未来像から一度離れてください。
心のトラブルは、健常者から見たら「なんで?」と思う状態かもしれませんが、感覚的には癌のステージ3くらいだととらえてください。
いつ心が暴走してもおかしくない状態です。健康になるのも、かなり長い道筋をたどります。原因や即効薬もないのです。

「○○をしないといけない」を捨ててください。
好きにさせる
自分の好きなことをさせましょう。不登校の段階にもよるのですが、「少しでも学校へ」という考えから離れて、自分の好きなようにさせてあげてください。
ゲームでも良いですし、運動でも良いです。博物館や科学館も良いですね。それから、勉強をしたいなんて言ってくれたらさらに良いです。知識や技能を身に付けることができたら、学校なんて行く必要ないのですから。そのくらいの感覚でいてください。

どんな反応をされているかはわからないですが、本人も罪悪感と戦っていることを知っておいてくださいね。
自信のコップで満たす
子どもの心のコップを自信で満たしてあげましょう。さらには、子どものできることを増やしましょう。料理でも良いですし、運動のスキルでも良いです。自分が「できる!」と思うことで自己有用感というものが心に出てきます。
「これもできた。では、これもできるかな。」を繰り返します。
そうすると、自分の中で様々なことを処理するようになります。心のコップを自信で満たしていくと、自然となんでも行動ができるようになります。
物事を達成すると、脳の中でドーパミンという物質が出ます。これは幸せホルモンの一種で、お金をもらったときや、ほめられたときなどに出る物です。これを脳が覚えていけば、行動するごとにドーパミンが分泌されるので、行動の継続の力のもとになります。
運動させる
運動は効果的です。ほとんどの場合、自律神経の乱れから来ていることが多いので、朝太陽を浴びて、体を動かす習慣を作ることは、心身にプラスの影響を与えます。
気持ち良い感じを受けることで脳の中にセロトニンというものが分泌されます。これも幸せホルモンの一つで、子どもの感情に良い影響を与えます。
セロトニン、ドーパミンという幸せホルモンの他に、オキシトシンという抱きしめたときに出る幸せホルモンがあります。たくさんの愛情をそそいであげてください。

食卓が楽しいと「生まれてきて良かった!」と子どもは思うようですよ。
寝させる
大人は8時間の睡眠が必要ですが、子ども達には、9~10時間必要です。これは、医学的な根拠に加え、私がみてきた教育的根拠です。優秀な子や優しい子、心にゆとりがある子はたっぷり寝ます。十数年も年賀状を送る優しいリーダーであった子は、7時に寝ていました。
たくさん寝た次の日の朝は気持ちが良いですよね。セロトニンがたくさん出ているのだと思います。夜更かしをさせずにたくさん眠ることができると良いですね。

私が不登校になりかけていたときは、睡眠時間は2~3時間くらいでした。ずっと読書をしていました。
待つ
あとは、ひたすら待ちます。笑顔になるまで待ちましょう。1日で終わるかも知れないですし、10年間かかるかも知れません。「笑顔が多いときに、最近どうして笑顔が多くなったの?」と尋ねられたら尋ねましょう。
楽しいことをたくさん話して、たくさん体験して、子どもを見守るしかありません。子どもは今は心の病気かもしれません。一緒にいてたくさんの愛を与えて、心のコップを満たしてあげてください。

不登校のとき、担任の先生はあまり好きではありませんでしたが、電話で学級の様子などを聞けたのは嬉しかったです。
気をつけること
結果をあせること
結果を焦ってしまい、多くの人が失敗しています。
家から出ない引きこもりの中高年の人口は、61万人です。
不登校は、その中の予備軍です。長い人生ですので、学校があっている期間になんとしてもという気持ちはわかるのですが、焦って恐怖心だけをあおって失敗していくケースを何度もみてきました。

一番多い失敗は、無理矢理ひっぱって連れていくことです。学校に対する嫌悪感や大人に対する不信感しか生みません。特に10歳以上の子にはやめた方が良いです。
長い年月をかけて治していく病気と同じように焦って登校させる必要もないのです。学ぶ方法や働き方なんて今の時代いくらでもあります。
劣等感をつけてしまうこと
劣等感をつけてしまえば、さらに悪い方向に行きます。
ヒステリックになりながら、「どうしてこうなってしまったの!」と尋ねてしまうと、子どもたちはさらに追い込まれてしまいます。
「ああ、自分はなんてダメなんだろう。」と自身でマイナスのレッテルを貼ってしまうと、なかなかそれを崩すのは難しいです。
あくまでもプラスのこえかけをしていきましょう。
状況は変わるということ
状況は日々変わっていきます。
子どもの状態は、より神経質になり、より学校に対して不信感や不安感を持つ可能性はあります。
また、家族の考えや自身の考えも日々揺れ動いています。
そのように状況は常に変化していますから、変化に追いつけないと、正しい判断が下せなくなります。
必ず定期的に状態をチェックしてもらって、アドバイスをその都度もらってください。
それでも不安。もしくは解決しないときは
専門家に相談しましょう。
・学校の先生
・学校のカウンセラー
・心療内科
・親戚や近所で詳しい人
家族に1人不登校がいるだけで、驚くほど心理的負担が大きくなります。それを、家族や近所の友達やその親、担任や学校、そして自分を傷つけてしまいます。メンターとなる方を必ずそばにいられるようにしておいてくださいね。
意外と知られていないのですが、学校の先生方は心理学のスペシャリストです。大学の講義でもありますし、教員採用試験の試験科目でもあり、研修でも学んでいます。親しい先生や担任の先生に相談されてみてください。

絶対に一人では、抱え込まないでくださいね。必ずだれかが味方になります。答えは、AかBだけでなく、Cという正解もあるかも知れません。大事なのは、誰かに一人で抱え込まないことです。
まとめ
原因というのは、ほとんどないのですが、あえて挙げるとするならば、以下の6点が多いと考えられます。
・人間関係
・学校という空間
・起立性調節障害
・学習性無力感
・HSC
・経済的理由
子ども達の口車に乗るのではなく、子どもを理解する上で必要なので、理由を挙げています。子どもがなぜ、その理由を挙げるのか、その理由を言うことは子供はどのような状況なのかをしっかり理解してあげたいですね。
対策としては以下の6点を挙げました。
・一度全て捨てる
・好きにさせる
・自身のコップで満たす
・運動させる
・寝させる
・待つ
まずは、子どもの心の調子を整えましょう。何かをしだすのはその後です。また、その後は、子どもの心は傷つきやすくなっています。また、再発しても動揺しないように心の準備をしておきましょう。
また、結果を焦ったり、子どもを追い詰めたりする行動には気をつけましょう。逆の効果に働きます。親の心も強くは無いので、専門家と一緒に良いかかわり方を見つけられるとよいですね。

長い期間になると思いますが、できることからしていきたいですね。それでは。