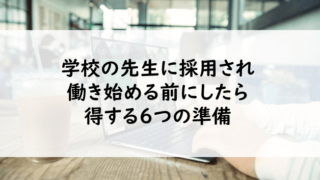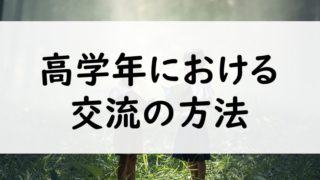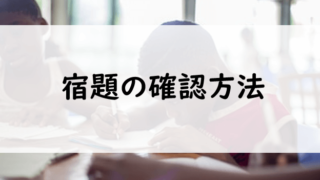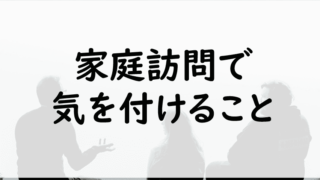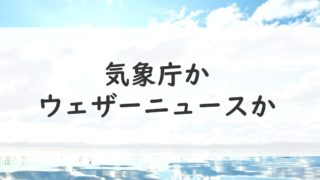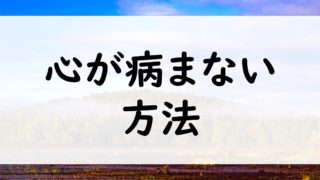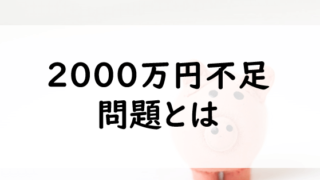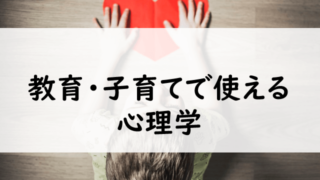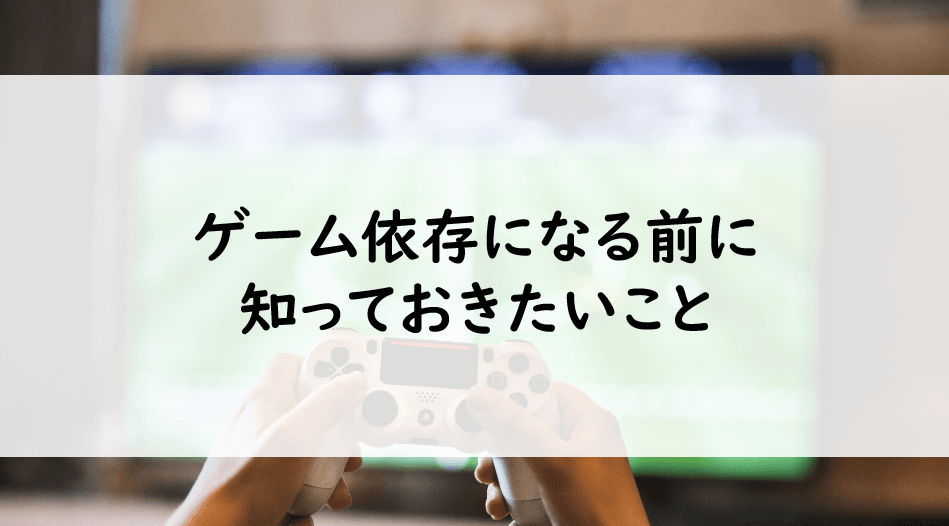子どもがゲーム依存で困っています。注意しても聞かないし、このままだったら、ゲームの世界にのめりこんでしまいそうで心配です。

よくある質問ですね。子どもがゲーム依存症になって切れやすく、引き込もりにならないためにも早めに対策をしておきましょうね。解説します。
近年、ゲーム依存・スマホ依存などそれがないと生活ができなかったり、いらいらして人を傷つけたりするという話をよく目や耳にします。
今回は、ゲーム・スマホ依存にならないための方法です。
お子様がゲームのためにひきこもりにならない方法を一緒に考えていきましょう。
現状の確認
お子さんの現状を把握しましょう。
・どんな種類のゲームに興味があるのか。 ・どこの国のゲームか。 ・なんのゲームをしているのか。 ・何時間しているのか。 ・依存し始めてどのくらいか。 ・誰と一緒にプレイしているのか
知ることができる限りの情報を集めてみましょう。実際にそのゲームをしてみると良いかもしれません。
最近は、「動物の森」などの日本のゲームだけでなく、荒野行動、フォートナイト、マインクラフトが人気です。
まずは、子どもの目線に立ってみて、情報を集めてみてください。
子どものこととゲームのことを理解するにはまず、自身がゲームをしてみるのが一番です。

フォートナイトと荒野行動の人気はすさまじいですね。
ゲームのデメリットとメリット
当たり前のことですが、ゲームをするメリットとデメリットを整理しておきましょう。
子どもと話すときに使います。まずはゲームのメリットです。
ゲームのデメリット
・視力が悪くなる ・ゲーム上でルールは決まっているので、思考する場面が少ない ・コミュニケーションをする機会が減る ・多くの時間を費やす ・通常の生活をしていて問題解決する力がなくなる ・キレやすくなる ・お金がかかる ・ゲームができないとそわそわしてしまう ・潜在意識が変化する
ゲームのデメリットは無限に出てくるかもしれませんね。
特に不登校の子は、この世界から抜け出せなくなってしまうので、ある程度の距離をあらかじめとっておくことが必要になると考えています。
不登校の子は、場合によっては、ゲームが心の栄養になる場合もあるので、安易に完全否定はしません。
しかし、ゲームに依存しすぎては人として自立できなくなってしまうことは変わらないので、そこは気に留めておく良いですね。
また、自分の思い通りにならないときにどのような表現をしたらいいかわからないので、全力で怒る、つまりキレる状態になりやすくなります。
潜在意識も変わることを知っておきたいです。人を殺すゲームをしていると、自分では気づかない内に心の底の方で悪い心が育っていくようです。
この記事をご覧になるということは、ゲームのデメリットをみえているということなので、この程度で割愛しますね。

私が担当する不登校の子は、全員フォートナイトをしていました。
ゲームのメリット
・友達との会話に入れる ・自信がつく ・簡単でわかりやすい ・内容が面白いものがある ・夢中になることができる ・体力を使わない ・内容によっては学習になる
ゲームをするには、デメリットもあれぼ、メリットもあります。
ゲームは子供達の欲をくすぐる環境が多く揃っています。
日常を抜け出して冒険に行け、モンスターや武器をコレクションでき、少しだけがんばればたくさんのご褒美をもらうことができます。
仲間とも簡単に意思疎通できて、自分がいなければ誰かが困ってしまうという状況に陥ってしまいます。
現実世界では、大人たちから厄介者扱いを受け、役に立てない状況があり、ゲームの世界では自分がいなければ世界が回りません。
心理学でいうところの、自己存在感や自己有用感はゲームの中でしか育まないものになってしまうというなんとも残念な環境で子供たちが過ごしている状況にあるのです。
また、ゲームをすることでゲームつながりの友達は増え、逆にゲームをしていない人は友達の話題に入れず焦ってしまう状況があるようです。

ゲームのメリットを理解しておかないと、子どもとつながれません。
なぜ子どもはゲームに夢中になるのか
適切な課題性
ヴィゴツキーという心理学者は次のように言っています。
「学習者にとって、最適なレベルの課題こそ必要。」
発達の最近接領域という考え方なのですが、達成感がよくでるものは、簡単すぎてもだめで、難しすぎてもだめです。
本人に合ったちょうどよい課題というものが必要になります。本人が少し頭や手を働かせて導いたものにこそ達成感ややりがいというものが見出せるようになるのです。
つまり、ゲームというのはよく研究されていて、ちょうどよい苦労をして、ちょうどよい戦い方をして、ちょうどよくクリアできる。だからこそ、夢中になれるのです。

年間数億円をかけて研究されているので、子どもが夢中にならないはずがありません。
話題性
友達の存在は大きいです。友達との話題がそのゲームだけというのは少なからずあります。
子どもの休み時間の会話を聞いていたら次のような内容の話をしていることがわかります。
・なんのキャラクターを使っているか ・どこまで進んだか ・ゲームのクリア情報 ・ゲームのお得情報 ・感想 ・次の遊びの約束
やはり、好きなことを話すときの子どもの表情はいいですね。そのこと自体は問題視をしないでほしいです。
過度の使用が問題ですので、ゲームは楽しいという思想は共感してあげてくださいね。頭ごなしの話し合いはうまくいきません。

ゲーム好きの子から、ゲームを切り取るのは難しいと思われてください。。
達成感
ゲームをクリアすると、次のようなアクションが生まれます。
・クリアという表示が出る
・音声がなる
・クリア時に演出がある(紙吹雪・拍手)
・協力した仲間から称賛の拍手がある
・クリアしたらポイントが手に入る
・クリアするとアイテムがもらえる
物事を達成したり、称賛されると脳の中にドーパミンが放出され、快感を覚えます。
さらに視覚情報や聴覚情報、脳内からの刺激ですので、より信ぴょう性が増してきます。すると脳はその行動が正しいと認識し、行動を繰り返すよう指示を出します。
これが、ゲームから抜け出せなくなる理由です。
「自分のしている行動は、人のためになっている。」
「努力したのでレベルが上がったんだ。」
「もっとやりたい!」
「今やめるとこれまでの努力がもったいない。」
このように思うことで抜け出せなくなります。

これを現実でもすればよいのですが、実際は勇者ではなく怒られっぱなしの不自由で平凡な子どもなわけで、逃げたくなるのもわかりますね。
ゲーム依存にならないための10の方法
ゴール・目標をつくる
週に6回。週に14時間以内と明確に目標を立てましょう。
簡単なものでいいです。ゴール・目標をつくりましょう。大きな目標と小さな目標があるといいです。まずは、大体でいいので10分間ゲームの時間を短くするとか、1日だけゲームをしない日をつくるなどでも構いません。
最終的にどのくらいのものになれば子どもと話しましょう。場合によっては大人だけで話しましょう。
ゲームの良さや悪さを一緒に考える
「ゲームをしっぱなしだと馬鹿になる。勉強をしなさい。」という声かけは、ナンセンスです。子どもは心を閉ざし、真剣に大人の言葉と向き合うのはやめてしまいます。
そうではなく、
「ゲームはみんなでできて楽しいね。」 「今とのところ、上手なんだね。」
などといって共感してあげてください。
「でも、やりすぎたら目が悪くなってしまうね。」
「人と話すとき、緊張しちゃうね。」
などと話をしましょう。
共感をすること、そこから一緒に考えてほしいです。
ゲームをする場所を決める
・リビングでする。
・みんなといるところでする。
・自分の部屋ではしない。
実は、これは効果的です。なぜかわからないですが、ゲーム依存の子は自分の部屋でゲームをしがちです。
テレビ型のゲームは指示ができるのですが、最近のゲームは、ポータブルです。
こういうルールを決めないと、自分の部屋に閉じこもり、24時間ゲームをし続けるという状況になってしまいます。

自分の部屋以外でさせましょう。
ゲームの使用時間を自分で決めさせる
ゲームの使用時間は、自分で決めさせると良いでしょう。大まかに決めておいて、あとは自分で決めさせる。そのことで、自己決定能力がつきます。
・家に帰る。 ・宿題をし、明日の用意をする。 ・ゲームを1時間する。(夕食までの時間) ・夕食を食べる。 ・風呂に入る。 ・20時までゲームをする。 ・20時からは本を読む。 ・21時に寝る。 ※ゲームの時間は2時間以内。
何時までに風呂に入らないといけないから、何時までにゲームをして、次に…などと、見通しをもって生活ができます。
ゲームの時間が2時間は長すぎませんかという質問がくると思います。しかし、ゲーム依存の子は何時間までもできます。もちろん睡眠時間を削ってでもできます。それらのことを考えると、2時間というのは遥かに遠い数値です。21時に就寝も難しいでしょう。
お子様の実態に合わせて一緒に目標をつくってみてください。

食事中もゲームをしていたら、止めてくださいね。
ルールを守れたとき・守れなかった時の約束をする
・約束を守れなかったら、お小遣いを減らす。 ・たくさん約束が守れなくなったら、使用を1日ダメにする。
などのルールを守れなかったらどうするか決めましょう。
あからさまにゲームから遠ざけるというようにするのではなく、あくまでこれは約束を守れなかったときにするものだという認識をもってください。
「とにかく親は自分にゲームをさせたくないんだな。」と思わせてしまうと、逆にしたくなってしまうのが子どもです。心理の逆をつかせないように一歩先の心理をよみましょう。
確認アプリ・機能を有効活用する
カレンダーに、◎時間▽分と記入していく。
最近ではゲームの管理アプリや、テレビやゲームの機能で時間を測れるものがあります。
今自分が何時間ゲームをしているか。それがわかるだけで客観的に自分がどのくらいいているかわかります。
カレンダーなどに◎時間〇分とゲームをした時間を書いて、次の目標設定につながると良いですね。
ルールを設定するときにぜひ活用しましょう。

意外とこれは守ってくれます。
読書や学習スポーツなど他に夢中になれるものを見つけさせる
ゲーム以外に夢中になれるものを見つけるのを手伝いましょう。学校の課題や、スポーツ、読書など好きなことをさせてみましょう。
また、ゲームから抜け出すのに、ゲームという手もあります。本人も抜け出したいという思いがあるときに、違うゲームをさせてみましょう。
成功例に、フォートナイトから抜け出せない子にどうぶつの森をさせてみたら、フォートナイトから抜け出せたうえに、どうぶつの森が飽きてゲーム依存から抜け出せたということがありました。
ちがうものに目を向けさせるのが有効か手だてです。

私は親から本だけは小遣いではなく、親のお金で買ってもらっていました。そのおかげで小説をたくさん読むようになりました。
習慣化させない
よくある間違いで「一日◎分ルール」というものがあります。これは、お酒の「1日に缶一本ルール」と同じで、逆に習慣化させてしまうものになります。
習慣化させないためには、「週に◎時間ルール」「週に5回ルール」など子どもと一緒に対策を考えましょう。
交換条件を設ける
宿題をしたら30分。通信教育をしたら20分。草取りをしたら30分など交換条件をして成功した例もあります。
ただこれは、非常に管理が難しく、検証するのが難しいですが、管理ができる子どもならば有効です。
また、好きなだけしていいが、○○だけはするなど、という交換条件も考えられます。
ゲームだけにならないようにするためにあの手この手で子どもとかかわっていかないといけないですね。

これもあくまでゲームから遠ざけるための1手です。より時間がかかることをさせて、ゲームから遠ざけましょう。
視覚化
目に見えるようにルール作りをしましょう。自分でルールを決めさせて、守らせる。その繰り返しですが、子どもたちはすぐ心意気が変わります。
何かに書かせて貼らせておくなど、目に見える支援をしましょう。
私は、大体2週間経ったら貼りものは張り替えます。それと同時に振り返らせ、また次の目標を立てさせます。その繰り返しでよくなっていきます。

大人との約束は、数日後には破られてしまいます。紙に書いて貼っておきましょう。
まとめ
・ゲームのメリットとデメリットを理解しましょう。
・ゲームは何億円もかけて開発されているので子どもは夢中になる。
・10の心がけを1つでもよいので実践していきましょう。
ゲームを子どもがなぜし、夢中になるのはなぜなのか、また対策をするにはどうすればいかは、時代によって考え直さないといけませんね。
子どもたちが豊かに児童期を過ごすには、ゲームは欠かせない存在ですし、うまく付き合えないと大変なことになってしまいます。
ご家庭で正しく向き合えるようなルール作りをしてから始められてくださいね。

長文読んでいただき、ありがとうございました。何かの役に立てると嬉しいです。それでは。