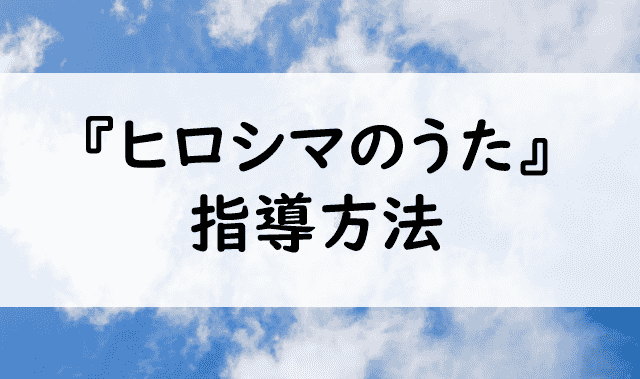今西祐行さんの書かれた「ヒロシマのうた」は、単元の終わりに平和教材を紹介するだけなので、さらっと読み流して他の平和の本の紹介の方に移ってもよいでしょうか。Tシャツやタイトルなども深く考えてもよくわからなくて…。

そうですね。それは少しもったいない気がします。確かに、単元末には平和学習とつなげますが、それだけでは、せっかく今西祐行さんが考えた文学が無駄に終わってしまいます。

やはり、この教材も読み取りをしないといけないのですね。よろしければ、どのようにするかを教えてください。

わかりました。解説します。
今回は今西祐行の『ヒロシマのうた』の指導方法。
平和学習を中心とした読みの学習です。平和学習への読書を推進する教材と思ったら、極端に解釈の難しいワイシャツ問題などが出てきます。
Yシャツに込められた思いとは何なのか。
「ヒロシマのうた」とは、何なのか。
今西祐行さんとは、どのような作家なのか。
一緒に考えていきましょう。
教材研究編
作者である「今西祐行」とは
まず、作品を知る前に作者について知ることが大切です。作者である今西祐行とはどのような方でしょうか。
略歴は以下の通りです。
1923年東大阪市生まれ。
1943年学徒出陣で海軍に入隊。
1945年被爆直後の広島へ救援隊として赴く。終戦。
1947年(昭和17)早稲田大学仏文科入学。
1956年幼児の心の世界を描いた『ゆみこのりす』で日本児童文学者協会新人賞を受賞。
城を守る仕掛け橋をつくって殺された仲間たちへの贖罪に、民衆のための堅牢な橋づくりに命をかけた石工頭岩永三五郎を描いた『肥後の石工』で、1966年日本児童文学者協会賞。1967年国際アンデルセン賞国内賞を受賞。
『浦上の旅人たち』(1969。野間児童文芸賞)のほか、『ねことオルガン』(1962)、『太郎コオロギ 童話集』(1965)、『いればをしたロバの話』(1971)、『一つの花』(1975)など。
また、被爆直後の広島での体験は彼の作品の大きなモチーフになったが、その代表作が『ヒロシマのうた』(1970)。
1992年紫綬褒章受章。
2004年 心不全のため亡くなる。(81歳)

戦争時代の絵本作家です。「一つの花」「ヒロシマのうた」は47歳のときに書かれました。その他の作品は、学校の図書館を調べられたら、3・4冊は出てくると思います。是非、借りて読んでみましょう。
以前は、「一つの花」、 「太郎こおろぎ」、「むささび星」、「はまひるがおの小さな海」、「金の魚」などで、国語の教科書すべてに 今西祐行の作品は登場しました。現在は、「ヒロシマのうた」と、「一つの花」だけです。
暗示性が高い、「ヒロシマのうた」を読解するには、「すみれ島」や「ゆみ子とつばめのお墓」なども読まないといけません。
教材文分析
物語のあらすじ
次に、多くの方は読んでいると思われますが、「ヒロシマのうた」の作品の粗筋についてです。話が長いのでポイントでまとめました。
- 水兵である稲毛は、原爆が落とされた30キロ先の呉にいた。
- 赤ん坊をだく母親(長谷川清子)を見かけたが、赤ん坊の母親(と思われる人)は亡くなった。
- 赤ん坊の名前は「ミ子」と思われる。
- 水兵は、「ミ子」を預かり、通りすがりの人に預けた。
- ラジオのたずね人の時間に、赤ん坊を預けた水兵さんを探していると放送があった。
- 放送局に行って連絡先を聞き、連絡した。
- 赤ん坊は、夫婦の亡くなった子供の代わりの「ヒロ子」として育てられていた。
- ヒロ子の家は、主人が亡くなっていて、経済的に苦しく、育ての親は「ヒロ子」を元の親類に預けようとした。
- 3人は、夏に会う約束をした。
- 「ミ子」は小学一年生になっていた。
- 「ミ子」の産みの親(?)の話をすると、育ての親は「ヒロ子は自分が育てると決心した」と話す。
- 中学を卒業した時にまた会う約束をした。そのときまで親が違うという真実を打ち明けないと話した。
- 別れるとき、ヒロ子は暗いかげがあった。
- 親戚のおばさんから「拾い子」と怒られるので、真実を打ち明けたほうが良いか母から相談。
- 稲毛は、田舎を出て二人で暮らした方が良いと返事をする。
- ヒロ子の親2人は、広島に出て、洋裁学校に住み込みになった。
- 中学を卒業したヒロ子と原爆記念日に広島を観光。
- 川に面した食堂で灯篭が流れる。
- ヒロ子の母親の名札を渡し、母親の話をした。
- ヒロ子は、泣かずに「わたし、お母さんに似てますか?」
- 洋裁学校の一室に泊まった。
- 次の日、寝ずにヒロ子が作ったワイシャツを母親が見せた。
- ワイシャツの腕に小さな原子雲のかさと「S・I」と水色の糸で刺繍されていた。
- 母親は「ええ、おかげさまで、もう何もかも安心ですもの……。」
- 帰りの汽車の窓からそのシャツを受け取った。
要点だけをまとめても、かなりの量ですね。何回も通読するには、少し体力のいる教材です。

初読と、粗筋のまとめのときに通読するくらいで、あとは、部分的に読む方がよいでしょう。読むのが苦手な6年生を想定してのことです。
作品後半に集中する疑問
この作品は、作品の後半になるにつれて疑問点がほつほつと出てきます。
またそれは、子供たちが初めて読んだときに抱く疑問です。授業とは関係ところもあるかもしれませんが、あえて教材研究のために触れておきます。
「実母ではない」といつのまにか知っていた
ヒロ子の母親は、ヒロ子に対して、本当の母親は別であるということを伝えるのをためらっているような様子がありました。
しかし、実際に稲毛に会う時には、もう知っていたようです。
これは、おじさんからのいやがらせに対し、知らなければならない時があったのだと思われます。
母の発言の謎
「ええ、おかげさまで、もう何もかも安心ですもの……。」
この言葉は深いです。これだけで単元のめあてが作れるほどです。
このときの、安心というのは、不安な要素や心配事がなくなったということでしょう。
それでは、不安な要素がなくなる前の不安とはどのようなものだったのでしょうか。
不安に思っていたことまたは、心配していたことは、「経済的な不安」「原爆症に怯えること」「知ってショックを受けること」だったでしょう。
一度目に連絡してきたときは、このままヒロ子を育てていけるかを心配していました。経済的な理由と、原爆症で母が亡くなるかも知れないという理由からです。
2度目に連絡していたときは、親戚にいじめを受けているときでした。
そして、ヒロ子のことを考えて広島に出てきた。つまり、母親の心配事はほとんどがヒロ子のことでした。
「ええ、おかげさまで、もう何もかも安心ですもの……。」に言葉に修正を加えると、「ええ(よかったです)、(稲毛さんの)おかげで、(ヒロ子のことについて)もう何もかも安心です。」と解釈してよさそうです。

気にしていないと素通りしてしまうような会話文ですね。
ワイシャツの謎

原爆雲とイニシャル「S.I」(アニメ版は左胸・本文は腕)
なぜイニシャルなのか。なぜワイシャツなのか。なぜ水色なのか。なぜ原爆雲なのか。これは、この作品における重要な謎ですね。多くの子どもがこのワイシャツの原爆雲に疑問をもつでしょう。
まず、イニシャルの「S・I」とは何でしょう。死?稲毛?今西祐行?
これは、稲毛のために編んできたのですから、「稲毛」という風に解釈されることが妥当でしょう。ワイシャツなのも、稲毛が着るように仕立てたものだと考えるのが妥当です。
しかし、「本当に稲毛さんのイニシャルかな。」とゆさぶってみても面白いですね。
「s」でしたら、「真剣に」、「好き」、「誠実に(な)」…。
「I」でしたら、「生きていく」、「一生懸命」、「いろんなことがあっても」、「命」…。
これらの言葉が子供たちからは出てきそうです。組み合わせ次第では、主題に絡めて表現してくる子供もいるでしょう。
残る疑問は、「水色」と「原爆雲」です。「水色」からは、色の印象では、「さわやか」「すっきり」「きれい」と言った心情が感じられます。
しかし、「原爆雲」という重たらしいものが添えてあるがために強烈な違和感を子供たちは抱くでしょう。
これは、一つの解釈として、「原爆雲が私たちを引き合わせてくれた」というポジティブな側面をヒロ子はとらえているといってよいでしょう。
お母さんの話を聞いても泣かない強さをもったヒロ子。最後の「するどい汽笛を鳴らして、上りにかかっていく」というポジティブな描写からそのような心情がうかがえます。
戦争で命を落として悲しい話ではなく、戦争に真っ向から反対する激しい話でもなく、戦争をきっかけに始まっていく新しいスタートの印象が感じられます。

「すみれ島」や「一つの花」もそうですが、暗く悲しい話なのではなく、新しい時代を感じさせるさわやかな感じが今西祐行さんの特徴ですね。そういう意味で、それらの作品を読ませてもよいかもしれません。
わたしたちの思い出
広島の町を回っていた時に、次のような文があります。
私は記念日を選んだことを、後悔していました。記念のいろいろな行事は、何かわたしたちの思い出とかけはなれたものにしか思えなかった。
映像でみると、イメージがしやすいでしょう。(8’00頃)
私達というのは、私、ミ子の母親、ミ子(ヒロ子)、ヒロ子の育ての母親というのが妥当でしょう。
それでは、わたしたちの思い出とは何でしょう。これまでの本文を読んでいくと、以下のように整理されます。
- 赤ん坊(ミ子)をだく母親を見かけたが、母親は亡くなっており、今の育ての親に預けた。
- ラジオのたずね人の時間に、赤ん坊を預けた海兵さんを探していると放送があり、連絡。
- 主人は亡くなっていて、経済的に苦しく、「ヒロ子」を「ミ子」の親類に預けようとした。
- 夏に会い、「ヒロ子」は小学一年生になっていた。
- 「ヒロ子」の産みの親の話をすると、育ての親はヒロ子は自分が育てると決心した。
- 親戚のおばさんから「拾い子」と怒られるので、打ち明けたほうが良いか母から相談。
- 田舎を出て、二人で暮らした方が良いと回答。
- 2人は、広島に出て、洋裁学校に住み込みになった。
- 15歳の夏に広島で再開。
本文の中から、読みとれる思い出は以上です。稲毛とヒロ子が直接会ったのは3回です。1度目は原爆直後、2回目は1年生のとき、3回目は15歳の夏です。
しかし、どうして「思い出とかけはなれたもの」になるのでしょうか。平和祈念行事と比べてみましょう。
平和記念行事とは、どのようなことをするのでしょう。
・原爆を許さないという主張。
・戦争を繰り返してはいけない主張。
・犠牲者への弔い。
というものでしょう。
これとかけ離れていると考えると、
・原爆を許したい ?
・戦争をまたしたい ?
・犠牲者を弔えない ?
となります。これは、あり得ませんね。
戦争を後世に伝えたいとする今西祐行さんの意志からもかけ離れます。もちろん、稲毛とヒロ子のこれまでの人物像からそれは考えられません。しかし、浅く読んだ子ども達が、このように誤読してしまう子どもがいるかもしれませんので、ご注意ください。
それでは、別の視点から考えてみましょう。ヒロ子から送られたワイシャツについてです。
前述の通り、後ほど渡すワイシャツには、「腕に小さな原子雲のかさと「S・I」と水色の糸で刺繍されていた。」とあります。これらは、原子爆弾に負けずに強く生きる3人の希望が表れていると感じます。
これらのことからわかるように、原爆後の生活というのは、決して誰かを恨んだり呪ったりするのではなく、幸せに向けて強く前を向いて過ごしてきたことが感じられます。
それらが、だれかを責める反戦運動などとは、少し異なると感じていたのではないでしょうか。
「汽車はするどい汽笛を鳴らして、上りにかかっていました。」
この描写は、一見遠ざかっていく別れのシーンを表していますが、これからの3人の人生を表していもいます。

この「するどい汽笛を鳴らして、上りにかかっていく」という表現は逃したくないですね。
自分の存在感を表し、さらに坂道を登っていきます。
さらに、「上っていく」のではなく、「上りにかかっていく」という言葉から何か戦っているような印象を受けます。
これらのことから、3人はこれからの人生は問題と戦いつつも、力強く突き進んでいくということがわかります。
ヒロシマのうた
単元の導入時に聞いておきたい質問として、「ヒロシマのうたってどんな歌だと思う?」があります。
初読の後に、「どんなうただった?」と尋ねたいですね。

歌なんてなかったけど・・・。
その通りですね。うたなんて一曲も入っていません。それでは、なぜ、「ヒロシマのうた」というタイトルなのでしょう。また、どうしてカタカナなんでしょう。
漢字の「広島」ではなく、ひらがなの「ひろしま」でもなく、カタカナで「ヒロシマ」と書く理由は、特別な意味合いを含んでいるということになります。
それは、普段のものとはちがうという意味でつかわれることもありますし、原爆が落とされたということをイメージさせたいということもあります。
作品で使われている「ヒロシマ」は、私たち3人がヒロ子をめぐる思い出としての「広島」という意味があります。そういう意味での「ヒロシマ」ということでしょう。
それでは、「うた」はどうでしょうか。実は、これは、教科書になって、「歌」が「うた」に変わりました。また、絵本によっても「歌」か「うた」かで異なります。
もちろん習っていない漢字では、ありませんので習っていないからという理由ではなさそうです。すると、意味を考えてほしいという教科書会社のメッセージとしてもとらえられます。
それでは、どのような意味を捉えられればよいのでしょうか。
「歌」を辞書で調べてみると、「拍子と拍をつけて歌う言葉の総称、または、それを歌うこと。」と出てきます。今回の場合、拍子も拍もありませんから、「歌」本来の意味ではありません。
「歌」の語源は、「(気持ちを)訴える」こととあります。こちらが使えそうです。
「ヒロシマのうた」。つまり、これまでの作者の読みとってきた考えとしては、ヒロシマが訴えたいこととは、「恨みや怒りではなく、前を向いて歩こう」と感じます。
これを学習にするのは、至難の業でしょうか。

「すみれ島」や「ちいちゃんのかげおくり」などの関連図書を利用し、今西祐行の作品の主題傾向をとらえると、わかってくるかも知れませんね。
指導の目標
高学年の指導目標
現在の学習指導要領には、高学年の「読むこと」には以下のように書かれています。
イ 目的に応じて,本や文章を比べて読むなど効果的な読み方を工夫すること。
エ 登場人物の相互関係や心情,場面についての描写をとらえ,優れた叙述について自分の考えを まとめること。
オ 本や文章を読んで考えたことを発表し合い,自分の考えを広げたり深めたりすること。
カ 目的に応じて,複数の本や文章などを選んで比べて読むこと。
メインは、カの「 目的に応じて,複数の本や文章などを選んで比べて読むこと」になります。
今回の目的は、主に戦争についてもっと知識を増やし、関心を高め、考えを深めるというもになります。
物語を通して、戦争中の出来事に関心をもたせ、平和への主張につなげていきたいです。
教科書に書かれている目標

東京書籍の教科書には次のように書かれています。
『本を読んですいせんしよう。』
・関連する本を読み、物語を深く味わう。
・自分の感想と深く関わる文章や言葉を用いてすいせんする。
最終的には、関連図書を読んで、推薦する文章を書きます。
戦争に関する文章を読んで、より知識が増え、考えが深まったものを紹介できるとよいですね。
推薦の活動ですが、推薦されたものを読むという子供はなかなかいないので、その場でしっかり聞くということを徹底させると良いですね。

学級文庫に置いていてもなかなか読みません。6年生ですから。
授業実践編

ここからは記事の更新中です。しばらくお待ちください。
本文を読み、単元の流れをつかむ
・初めて読んだ感想(単純な感想+疑問)
・意味調べもできそうであったら同時に行う。
初めて読んだ感想を書かせましょう。
そのとき、感想だけになって終わることもあるので、「登場人物のしたことで疑問に思ったこと」や単純に「疑問に思ったこと」を書く欄を設けておくと、疑問が共有されて問いになり、読みのめあてが立てやすくなります。
- お母さんが亡くなってかわいそうだと思いました。
- しんせきの家でもいじめられていてかわいそうだと思いました。
- 今の時代は恵まれているなと思いました。
- ヒロ子ちゃんは亡くなった母親の話を聞いて泣かないなんて心が強いなと思いました。
感想文は、戦争教材ですから、「○○がかわいそう」、「○○はよかった」が多くなるのではないでしょうか。あくまで通常の学校で、通常の指導をしていたら自然とその感想になると思います。
しかし、疑問に思ったことは、違います。
- なんで自分で育てようとしなかったのか。
- なんでいいことをしていたのに、上司に怒られてしまったのか。
- なんで最後に渡したTシャツにはきのこ雲が書かれてあったのか疑問でした。
- なんでしんせきの人はヒロ子ちゃんをいじめるのか。
- なんで住み込みで服をつくる学校に行ったのか。
- なんでわたしは安心したのか。
- ヒロシマのうたとは?
これをご覧になってわかるように、玉石混交の疑問になっています。戦争当時のことなので、突飛な疑問が多々出てきます。それは、時代が違うから当時の当たり前がわからないからです。
これはこれで、いいことなので、教えることと考えさせることを分けて、曖昧にしないことが大切です。
例えば、赤ちゃんの所へ行き怒られた理由として、部隊から勝手に離れ、勝手な行動をとることは軍隊としては絶対に許されなかったからという理由は教師が伝えて良いです。
逆に、Tシャツの刺繍の意味やタイトルは、登場人物や作者と読者をつなぐ大切なものですので、教師が伝えてはいけません。
このように、読む活動が深まるように、読みのめあてにつながるように整理してあげることが大切です。
単元のめあてをつくる
疑問を発言させ、問いになり、読みのめあてをつくる。
物語を読んで疑問に思ったことを話し合わせましょう。
次に、疑問に思ったことで共通することがあると思うので、それをまとめて「問い」にします。
最後に、それらを「読みのめあて」として整理しましょう。

厳密にはそこまでしなくていいですが、話し合いながら気になっていくのもありでしょう。あまりよくないのは、めあてが無くて何となく読んでいることです。子どもたちの自然な問いを大事にしたいですね。
高学年なので、全員に発言させてもいいですし、グループで話し合わせてまとめたものを発言させる形式でもよいです。実態によると思われます。
わからない言葉の意味調べをする
・意味調べの表を作ります。
・画像検索や動画検索なども使わせましょう。
これからの時代、わからない言葉はすぐに調べさせる習慣をつけさせたいです。辞書ではなく、できればタブレットで調べさせていきたいですね。
設定の確認をする
「時」「場所」「人物」「したこと」の確認
ある程度の場面で分けて、「いつ」「どこで」「だれが」「どうしたか」をまとめさせていきます。
(※ノートは後日作成します。)
子どもたちの読みのめあてを解決する
課題別、グループ別課題にして読み、読んで考えたことを発表させる形でも面白いですね。
時間の都合上、そうしている学校も多いのではないでしょうか。
安心に至った理由を読みとる。
「なにもかも安心です」
「なにもかも」の中身を明らかにすると母親の心情がわかりますね。
育ての母親の生活や経済面でしょうか。
ちがいますね。母親とヒロ子の関係、ヒロ子の今後や将来についてですね。読み解くヒントを与えたいです。
子を想う親の気持ちは、何世代を越えても変わりません。
情景描写から理由を考える。
何が上昇しているのかを考えると、面白い描写になりますね。
ヒロ子親子の将来。
稲毛の期待。
広島市民の願い。
日本の再興。
様々なことを想像できるでしょう。
ワイシャツの原子雲の怒りや悲しみにさえ勝つ、思いや願いを考える。
これは、子どもたちによってさまざまな解釈ができますが、これまでの、ヒロ子の言動や稲毛との関係がヒントになってきます。
ヒロ子が原爆の恐ろしさに負けていない強さもっていること。
「ヒロシマのうた」とは何か、考える。
この件は、子どもたちだけで解決するのは難しいです。2段階クッションを挟んであげる必要があります。
「広島」ではなく、「ヒロシマ」と書かれてあります。その意味は何かな?
今の「広島」とは、違う意味かもしれないですね。
( ※と聞くと昔の広島、戦争当時の広島の人と出ます。)
「うた」の語源は、「訴える」です。それでは、この物語を通して、「ヒロシマ」は何を訴えたいのかな?
戦争に関する本を読む
・内容は短く、戦争に関する本を教師が選定する。
この単元は、本を紹介するのが主な活動ですから、本を読ませないといけません。実際に平和に関する本を読んで、感想を書かせましょう。

今西祐行さんの「すみれ島」等戦争シリーズや、朽木祥さんの「光のうつしえ」を抜粋したものがおすすめです。
本を推薦する
・1人1分くらいで読み終わるようにする。
・一人も内容が被らないようにする。
・「本の題名」「本の内容」「本を読んで考えたこと」の3段落構成で書かせる。
単調にならないように、画用紙に書かせたり、タブレットを使ってプレゼンした方が退屈しないですね。
まとめ
以上の流れで、十分読めていると思います。深入りし過ぎると難しく、軽すぎると戦争教材意図しては良くありませんので、初めの段階でふるいにかけることが大事です。

以上です。参考になったら嬉しいです。まだ、未完成です。完成までもうしばらくお待ちください。